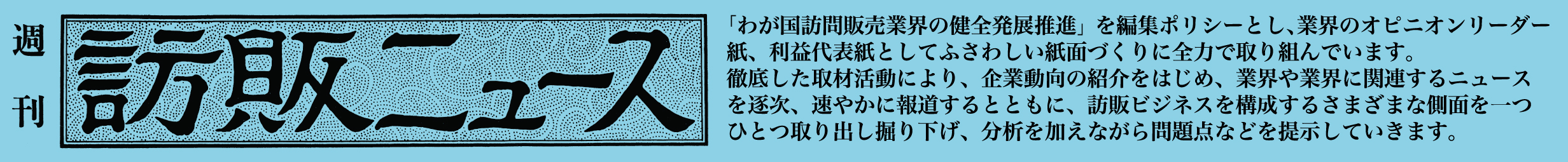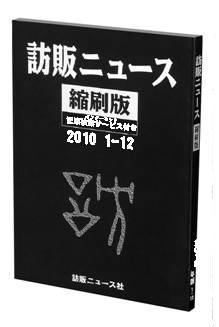社説 報酬支払い状況、明瞭な開示を
国内MLM市場が縮小傾向に入って久しい。拡大基調を維持する会社もある。しかし全体を見渡せば、底を打つ兆しは窺えない。背景にあるのは、フィールドの高齢化、商材差別化における苦戦、新興のギグワークとの競合、EC市場のシェア拡大、物価高に伴う買い控え等々。複数の要因が絡み合う。
中でも、もっとも大きな影を落とすのが「マルチ商法」というワードに表されるレピュテーション(社会認知)の低さだろう。一般社会は「マルチ商法」と無限連鎖講をほぼ同一視している。MLMあるいはネットワークマーケティング、連鎖販売取引と呼ばれる流通形態の一つとみなしていない。
なぜ、レピュテーションの低さを脱せないのか。大きいのは、「マルチ商法」と蔑視する認識が数十年以上に渡って社会に根付いてしまっていること。実際は、他の流通形態と同様に商品の販売から収益を得ており、組織の大部分を占める愛用者に支えられている。業界内部の人間にとっては自明のことだが、この訴えを業界の外に届けることを「マルチ商法」の壁が妨げている。
もう一つの大きな要因がある。MLMというビジネス自体が分かりにくいことだ。特に報酬プランは、一般の消費者にすれば複雑怪奇と思えておかしくないだろう。業界で当たり前のように使われている専門用語に始まり、会社によって異なるタイトル等の呼称、プランのモデル毎の差異といった点は、「マルチ商法」に近いレベルのハードルとなっている。
この障壁を引き下げる取り組みがない訳ではない。報酬を得られるまでのシミュレーションの説明が行われており、実際の報酬支払い状況を開示している会社は、ひと昔前に比べて格段に増えた。特に後者は、「儲かると誘われて騙される」といった懸念の払しょくに、ある程度貢献していると考えられる。世界でもっとも大きい市場規模をもつ米国では、支払い状況の開示が当然の慣行として定着しており、米系外資の大半は本国に習っている。
ただ、せっかくの報酬支払い状況開示も、実は難を抱えている。たいていの場合、タイトル毎の平均取得額やボーナスの種類毎の取得人数を開示するにとどまり、結局のところ、報酬プランの仕組みを把握していなければ理解が困難だからだ。
一般消費者にも理解しやすい開示手段はないのか。例えば、多段階販売(MLM)の登録制度を取る韓国では、訪問販売法に基づいて、取得額を基準とした人数やその構成比の開示を義務化している。参入規制という前提あってこそだが、その手法自体は参考に出来る。レピュテーションを求めるのであれば、一般社会に受け入れられる明瞭な開示が不可欠だ。
中でも、もっとも大きな影を落とすのが「マルチ商法」というワードに表されるレピュテーション(社会認知)の低さだろう。一般社会は「マルチ商法」と無限連鎖講をほぼ同一視している。MLMあるいはネットワークマーケティング、連鎖販売取引と呼ばれる流通形態の一つとみなしていない。
なぜ、レピュテーションの低さを脱せないのか。大きいのは、「マルチ商法」と蔑視する認識が数十年以上に渡って社会に根付いてしまっていること。実際は、他の流通形態と同様に商品の販売から収益を得ており、組織の大部分を占める愛用者に支えられている。業界内部の人間にとっては自明のことだが、この訴えを業界の外に届けることを「マルチ商法」の壁が妨げている。
もう一つの大きな要因がある。MLMというビジネス自体が分かりにくいことだ。特に報酬プランは、一般の消費者にすれば複雑怪奇と思えておかしくないだろう。業界で当たり前のように使われている専門用語に始まり、会社によって異なるタイトル等の呼称、プランのモデル毎の差異といった点は、「マルチ商法」に近いレベルのハードルとなっている。
この障壁を引き下げる取り組みがない訳ではない。報酬を得られるまでのシミュレーションの説明が行われており、実際の報酬支払い状況を開示している会社は、ひと昔前に比べて格段に増えた。特に後者は、「儲かると誘われて騙される」といった懸念の払しょくに、ある程度貢献していると考えられる。世界でもっとも大きい市場規模をもつ米国では、支払い状況の開示が当然の慣行として定着しており、米系外資の大半は本国に習っている。
ただ、せっかくの報酬支払い状況開示も、実は難を抱えている。たいていの場合、タイトル毎の平均取得額やボーナスの種類毎の取得人数を開示するにとどまり、結局のところ、報酬プランの仕組みを把握していなければ理解が困難だからだ。
一般消費者にも理解しやすい開示手段はないのか。例えば、多段階販売(MLM)の登録制度を取る韓国では、訪問販売法に基づいて、取得額を基準とした人数やその構成比の開示を義務化している。参入規制という前提あってこそだが、その手法自体は参考に出来る。レピュテーションを求めるのであれば、一般社会に受け入れられる明瞭な開示が不可欠だ。