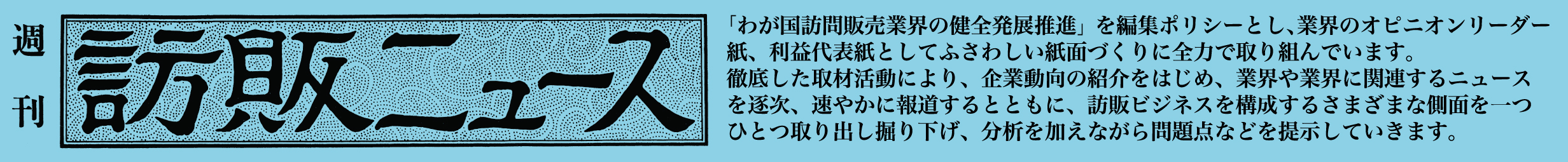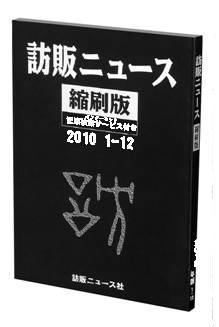社説 リアル接点の再構築が急務
6月16日に開催された訪販化粧品工業協会の定時総会において、西方和博会長(ポーラ)は、冒頭の挨拶で、「DXやOMOの利便性が近年注目されている。その一方で、リアルでのふれあいもあり、今後はこれが(今後の市場展開に)大事になっていくのでは。お客様にそのような場づくりを提供することが大切。訪販という顧客接点をどのように喜んでいただくか」と、OMOの活用に訪販ビジネスの発展があることを示唆した。
消費者のライフスタイルが多様化した現在、ニーズの多様化に合わせた商品やサービスが登場している。特に、デジタル・オンライン施策の導入は急速に進んでおり、西方会長が言及した通り、OMOが今後の主軸となっていくトレンドが強まっている。ダイレクトセリング化粧品市場では、サロンなどのリアル接点をベースとした手法が、ドア・ツー・ドアのような昔ながらの訪販スタイルに代わるビジネスモデルとして定着したが、時代の変化に合わせて、新たな顧客接点の創出が求められるようになってきた。そのカギとなるのが、OMOの活用ということになる。サロンビジネスへの転換は、およそ四半世紀前を起点とし、2010年代にピークを迎えた。一方、現在のOMOビジネスへの転換はまだ始まったばかりであり、最大手のポーラでさえ、今年から本格的にスタートする状況にあり、定着するにはまだ時間を要するとみられる。
化粧品業界全体を見渡すと、サロンビジネスへの転換が進んだ当時と大きく異なる点がある。それは、市場の二極化が進んでいることだ。ドラッグストアを中心に、コスパ重視の低価格帯アイテムが人気を集める傍ら、訪販化粧品のような、高機能・高付加価値で訴求する高価格帯アイテムが、ヘビーユーザーを中心に根強い支持を集めている。しかしながら、コスパ重視の低価格アイテムとはいえ、昨今は機能面も充実している傾向にあり、「美白」「エイジングケア」「シワ改善」といった分かりやすいフレーズでの訴求も積極的に行われている。加えて、昨今の物価高も相まって、ニーズを掴む傾向にある。その一方で、高価格帯アイテムを愛用している層では、近年、さまざまなトラブルを抱えつつも利用者を増やしている美容医療分野との競合も懸案事項となっている。では、低価格と高価格の中間に位置する中価格帯アイテムはどうかと言えば、業界関係者によれば「現状、もっとも厳しい」ようだ。
人と人のつながりを最大の強みとして市場を構築してきたダイレクトセリング化粧品だが、美容分野を取り巻く環境の変化に加え、老舗では販売員の高齢化などが進展している。猶予が少ない中、最大の付加価値である新たな「リアル接点」の構築が急務となっている。
消費者のライフスタイルが多様化した現在、ニーズの多様化に合わせた商品やサービスが登場している。特に、デジタル・オンライン施策の導入は急速に進んでおり、西方会長が言及した通り、OMOが今後の主軸となっていくトレンドが強まっている。ダイレクトセリング化粧品市場では、サロンなどのリアル接点をベースとした手法が、ドア・ツー・ドアのような昔ながらの訪販スタイルに代わるビジネスモデルとして定着したが、時代の変化に合わせて、新たな顧客接点の創出が求められるようになってきた。そのカギとなるのが、OMOの活用ということになる。サロンビジネスへの転換は、およそ四半世紀前を起点とし、2010年代にピークを迎えた。一方、現在のOMOビジネスへの転換はまだ始まったばかりであり、最大手のポーラでさえ、今年から本格的にスタートする状況にあり、定着するにはまだ時間を要するとみられる。
化粧品業界全体を見渡すと、サロンビジネスへの転換が進んだ当時と大きく異なる点がある。それは、市場の二極化が進んでいることだ。ドラッグストアを中心に、コスパ重視の低価格帯アイテムが人気を集める傍ら、訪販化粧品のような、高機能・高付加価値で訴求する高価格帯アイテムが、ヘビーユーザーを中心に根強い支持を集めている。しかしながら、コスパ重視の低価格アイテムとはいえ、昨今は機能面も充実している傾向にあり、「美白」「エイジングケア」「シワ改善」といった分かりやすいフレーズでの訴求も積極的に行われている。加えて、昨今の物価高も相まって、ニーズを掴む傾向にある。その一方で、高価格帯アイテムを愛用している層では、近年、さまざまなトラブルを抱えつつも利用者を増やしている美容医療分野との競合も懸案事項となっている。では、低価格と高価格の中間に位置する中価格帯アイテムはどうかと言えば、業界関係者によれば「現状、もっとも厳しい」ようだ。
人と人のつながりを最大の強みとして市場を構築してきたダイレクトセリング化粧品だが、美容分野を取り巻く環境の変化に加え、老舗では販売員の高齢化などが進展している。猶予が少ない中、最大の付加価値である新たな「リアル接点」の構築が急務となっている。