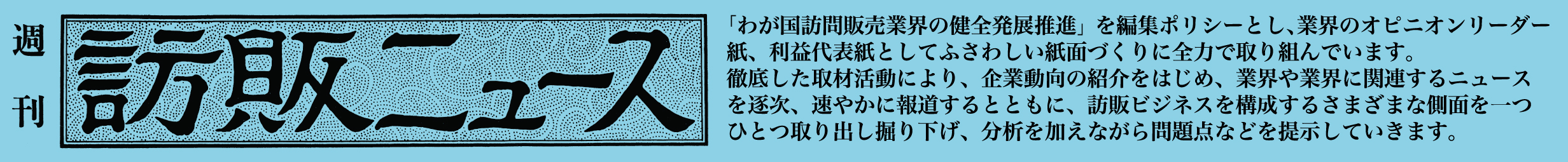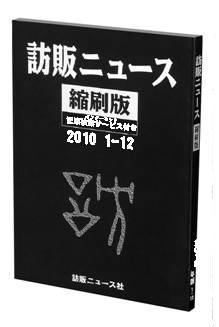社説 影響力問われる「エステJIS」
エステティック業界の第三者機関である特定非営利活動法人日本エステティック機構(略称・JEO)が、「エステティックJIS」(仮称)の策定を進めている。今年は規格の開発に向けた最終年度に当たり、今年度中に最終案を策定し、2026年度には認可を得て運用を開始する方針を示している。
「エステティックJIS」(仮称)は、JEOが2007年から運用する「エステティックサロン認証制度」を土台に、日本産業規格である「JIS」の認可を得ることで、現行制度より影響力をもつ制度として開発する狙いがある。2004年に設立されたJEOは、当時から消費者トラブルが絶えなかった業界健全化と、消費者の信頼確保を目的とした組織で、サロン認証制度、エステティック機器認証制度などの各制度を運用してきた。サロン認証は、「マル適マーク」を付与することで、消費者のサロン選びをサポートするという狙いがあった。2007年のスタート時は、約250のサロンが認証を受けたが、申請数は伸び悩み、現在は118サロン(25事業者)にまで減少している。昨今、脱毛サロンの倒産に伴う消費者相談が増加し、2022年度には2万件を超えた。健全化を掲げながら、業界全体に対して大きな影響力を確保できていないのがJEOを取り巻く状況だ。
そんな中、「エステティックJIS」(仮称)の策定が進んでいる。JEOはもともと、経済産業省がサービス産業の発展を目的に行った「エステティック産業の適正化に関する検討会」での話し合いを土台に設立が進められた第三者機関であり、今回の取り組みについても、経産省からJEOに制度のJIS化の話をされたことが発端となっている。JISは、日本国内の産業標準化の促進を目的とする産業標準化法にもとづき制定される任意の国家規格であり、我々の日常生活のあらゆる場面で活用されている。JEOでは、エステティックサービスの産業標準化を進めることで、エステティック業界のさらなる健全化を図るとともに、ルールの方向性を統一化、明確化したい意向を示している。
先ごろ公表された第二次原案では、モニター募集と称した宣伝・広告表示の禁止、おとり広告の禁止、脆弱な状況にある消費者への配慮、前受金の会計処理に関する要求事項などが盛り込まれ、JIS化によって、エステティックサービスに関わるトラブルの減少・解消を図る強い意思がうかがえる。一方、現行のサロン認証制度にも言えることだが、結局のところサロン当事者、関連業者にどこまで影響力をもたせることができるのか。特に、業界団体に所属していない、いわゆるアウトサイダーに対してどう訴求していくのか、今後の取組みが気になるところだ。
「エステティックJIS」(仮称)は、JEOが2007年から運用する「エステティックサロン認証制度」を土台に、日本産業規格である「JIS」の認可を得ることで、現行制度より影響力をもつ制度として開発する狙いがある。2004年に設立されたJEOは、当時から消費者トラブルが絶えなかった業界健全化と、消費者の信頼確保を目的とした組織で、サロン認証制度、エステティック機器認証制度などの各制度を運用してきた。サロン認証は、「マル適マーク」を付与することで、消費者のサロン選びをサポートするという狙いがあった。2007年のスタート時は、約250のサロンが認証を受けたが、申請数は伸び悩み、現在は118サロン(25事業者)にまで減少している。昨今、脱毛サロンの倒産に伴う消費者相談が増加し、2022年度には2万件を超えた。健全化を掲げながら、業界全体に対して大きな影響力を確保できていないのがJEOを取り巻く状況だ。
そんな中、「エステティックJIS」(仮称)の策定が進んでいる。JEOはもともと、経済産業省がサービス産業の発展を目的に行った「エステティック産業の適正化に関する検討会」での話し合いを土台に設立が進められた第三者機関であり、今回の取り組みについても、経産省からJEOに制度のJIS化の話をされたことが発端となっている。JISは、日本国内の産業標準化の促進を目的とする産業標準化法にもとづき制定される任意の国家規格であり、我々の日常生活のあらゆる場面で活用されている。JEOでは、エステティックサービスの産業標準化を進めることで、エステティック業界のさらなる健全化を図るとともに、ルールの方向性を統一化、明確化したい意向を示している。
先ごろ公表された第二次原案では、モニター募集と称した宣伝・広告表示の禁止、おとり広告の禁止、脆弱な状況にある消費者への配慮、前受金の会計処理に関する要求事項などが盛り込まれ、JIS化によって、エステティックサービスに関わるトラブルの減少・解消を図る強い意思がうかがえる。一方、現行のサロン認証制度にも言えることだが、結局のところサロン当事者、関連業者にどこまで影響力をもたせることができるのか。特に、業界団体に所属していない、いわゆるアウトサイダーに対してどう訴求していくのか、今後の取組みが気になるところだ。