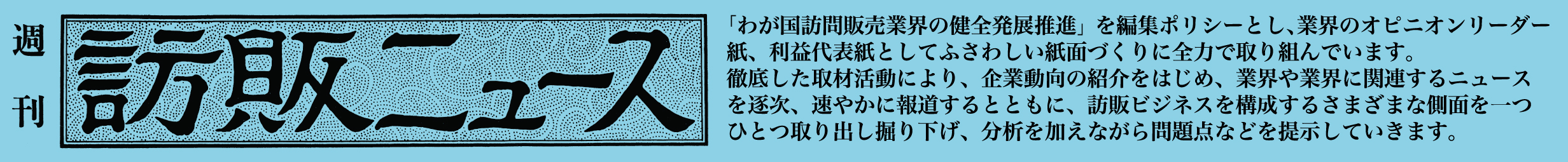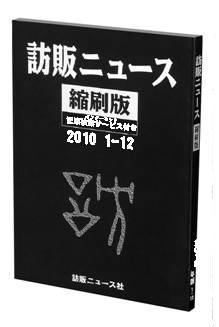社説 弄ばれたMLM、看過できない
国内政治は7月の参院選で自民党が大敗、衆参両院で少数与党の政権運営に突入した。綱渡りの運営を迫られ、野党側は多党化が一層進展。そして、国会の景色に劇的変化をもたらした先の参院選では、各党が激戦を繰り広げる中、ある野党をめぐり、MLM(連鎖販売取引)業界にとって看過できない事態が生じた。参政党の組織構築の手法と「マルチ商法」の類似性を示唆する情報がSNSを中心にあふれ、その結果として、MLMを悪質商法と断じる風評が著しく強まったことだ。
WEBではびこった情報の一つが、同党が過去に取り入れていたというランク制度なる仕組みと、MLMのマーケティングプランの類似性。勧誘した党員の人数に応じてブロンズ、シルバー、ゴールドといった称号を得ることができたという。このような情報がSNS特有の拡散力と相まってあふれかえった。
MLMは、その発端から「マルチ商法」という蔑称を背負ってきた。一般社会だけでなく行政も「マルチ」「マルチまがい」等の用語を当然のごとく使用し、悪質商法の一つとして代名詞化しているとさえ言える。
このような現状において何が起き得るか。その一つが今回の選挙戦で起きたレッテル張りだ。選挙はその大小にかかわらず、候補者が自陣を有利に運ぶため敵対陣営の荒探しに精を出すことが常。しかし、法的な違法性が問われる事実ではなく、容易に貶めることができるキラーフレーズとして「マルチ商法」が都合よく利用された。
「マルチ商法」という蔑視は今に始まったことではない。しかし、ことあるごとに取り上げられ、その度に業界の実態と大きく異なる悪評を助長すれば、そのダメージが蓄積されることとなり、レピュテーションの向上は更に遠のく。
MLM各社は愛用者の実需から収益を得て、税金を支払い、〝正業〟として事業を営んでいる。そうでなければ業界がとうに消え失せているはずだ。「マルチ商法」というワードの裏にチラつくねずみ講(無限連鎖講)との共通視は、業界人からすると心外でしかない。
行き過ぎた問題行為があれば特商法等による処罰を粛々と受け止め、自社のコンプライアンスの徹底に力を注いでいる。近年、「マルチ」トラブルの上位を占めてきたファンド型・投資型の事業者は、市場を荒らすアウトサイダーとして忌み嫌われている。
PIO―NETで「マルチ」としてまとめられているMLM系の24年度相談件数は4117件。過去20年で初めて5000件を割り込み、ピーク時の17%まで縮小した。このようなデータ一つとっても「マルチ商法」と切り捨てられるべき状況にはない。やはり看過できることではない。
WEBではびこった情報の一つが、同党が過去に取り入れていたというランク制度なる仕組みと、MLMのマーケティングプランの類似性。勧誘した党員の人数に応じてブロンズ、シルバー、ゴールドといった称号を得ることができたという。このような情報がSNS特有の拡散力と相まってあふれかえった。
MLMは、その発端から「マルチ商法」という蔑称を背負ってきた。一般社会だけでなく行政も「マルチ」「マルチまがい」等の用語を当然のごとく使用し、悪質商法の一つとして代名詞化しているとさえ言える。
このような現状において何が起き得るか。その一つが今回の選挙戦で起きたレッテル張りだ。選挙はその大小にかかわらず、候補者が自陣を有利に運ぶため敵対陣営の荒探しに精を出すことが常。しかし、法的な違法性が問われる事実ではなく、容易に貶めることができるキラーフレーズとして「マルチ商法」が都合よく利用された。
「マルチ商法」という蔑視は今に始まったことではない。しかし、ことあるごとに取り上げられ、その度に業界の実態と大きく異なる悪評を助長すれば、そのダメージが蓄積されることとなり、レピュテーションの向上は更に遠のく。
MLM各社は愛用者の実需から収益を得て、税金を支払い、〝正業〟として事業を営んでいる。そうでなければ業界がとうに消え失せているはずだ。「マルチ商法」というワードの裏にチラつくねずみ講(無限連鎖講)との共通視は、業界人からすると心外でしかない。
行き過ぎた問題行為があれば特商法等による処罰を粛々と受け止め、自社のコンプライアンスの徹底に力を注いでいる。近年、「マルチ」トラブルの上位を占めてきたファンド型・投資型の事業者は、市場を荒らすアウトサイダーとして忌み嫌われている。
PIO―NETで「マルチ」としてまとめられているMLM系の24年度相談件数は4117件。過去20年で初めて5000件を割り込み、ピーク時の17%まで縮小した。このようなデータ一つとっても「マルチ商法」と切り捨てられるべき状況にはない。やはり看過できることではない。