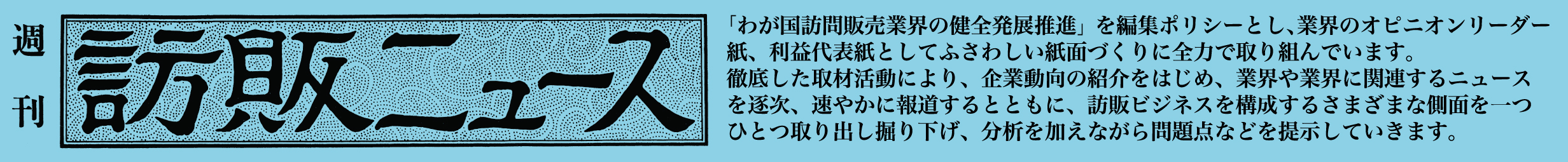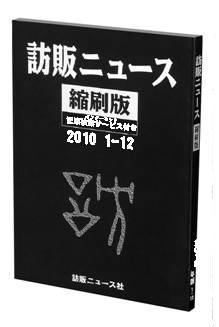社説 カスハラ問題、業界も対応必須
ダイレクトセリング各社の間で、カスタマーハラスメント(以下カスハラ)対策の取り組みが徐々に進みつつある。国は、従業員を守る対策を事業者に義務付ける改正労働施策総合推進法を6月に公布(施行は来年)。東京都は4月、同様の趣旨でカスハラ防止条例を施行した。「お客様」であっても、その言動が社会通念上許容される範囲を超え、労働者の就業環境を害する場合は、毅然とした姿勢で臨める法根拠が出来たことになる。
本紙は6月~7月に実施した業界アンケート(8月7日号)で、顧客等からカスハラを受けた経験があるか調査した。結果は「ある」が44%、「ない」が51%(残りは「分からない」)。半数を占めたのは「ない」だったが、設問ではカスハラを受けた時期を「直近1年間」に限定して聞いた。過去1年より前を含んで聞いた場合、「ある」の回答はもっと増えただろう。 項目選択式で聞いたカスハラの中身は、「話を遮る、話の揚げ足を取る」が最多。これに次いで「大きな声をあげる、睨む、物を叩く」「脅す、人格・服装等を中傷するような言動を行う」が多かった。記述式で寄せられた主なカスハラは「電話で長時間に渡って何度も要求を繰り返す」「消費生活センターをちらつかせて要望をのませようとする」「執拗な長文メールを繰り返し送る」など。従業員が直接的暴力を振るわれた事例はなかったものの、十分な業務妨害に相当する。
具体的対応として多かったのは「対応電話の録音、対応現場の録画」。回答企業の大半が実施しており、証拠を残すという観点からはすでに対策が進んでいた。また、過半数が「対応マニュアルの作成」や「対応のため各部署が連携する体制の整備」に着手していた。
国の推進法と都の条例は、カスハラ対応の方針を設けることを努力義務に求めており、中でも条例は、業界団体に対応方針の「ひな形」を作ることを推奨している。
健康関連取引適正事業団は7月、顧問弁護士の監修を受けた「対策マニュアル」を加盟企業へ配布。加盟企業の間では以前から顧客による暴言等のカスハラが度々問題化。健取団が対応の仲介や法的アドバイスを行ってきたといい、このことも素早い動きに結び付いた。一方、日本訪問販売協会は「ひな形」の作成に消極的ではないものの、今のところ具体的な動きは見られない。 本紙アンケートでは、5割の企業がすでに方針を設けたか、設けることを検討している旨を回答したが、方針の必要性を感じながら「特に設けていない」とした回答も4割を占めた。対応が遅れている企業は急ぐ必要があるとともに、業界団体が支援の体制を整えることの重要性も増している。
本紙は6月~7月に実施した業界アンケート(8月7日号)で、顧客等からカスハラを受けた経験があるか調査した。結果は「ある」が44%、「ない」が51%(残りは「分からない」)。半数を占めたのは「ない」だったが、設問ではカスハラを受けた時期を「直近1年間」に限定して聞いた。過去1年より前を含んで聞いた場合、「ある」の回答はもっと増えただろう。 項目選択式で聞いたカスハラの中身は、「話を遮る、話の揚げ足を取る」が最多。これに次いで「大きな声をあげる、睨む、物を叩く」「脅す、人格・服装等を中傷するような言動を行う」が多かった。記述式で寄せられた主なカスハラは「電話で長時間に渡って何度も要求を繰り返す」「消費生活センターをちらつかせて要望をのませようとする」「執拗な長文メールを繰り返し送る」など。従業員が直接的暴力を振るわれた事例はなかったものの、十分な業務妨害に相当する。
具体的対応として多かったのは「対応電話の録音、対応現場の録画」。回答企業の大半が実施しており、証拠を残すという観点からはすでに対策が進んでいた。また、過半数が「対応マニュアルの作成」や「対応のため各部署が連携する体制の整備」に着手していた。
国の推進法と都の条例は、カスハラ対応の方針を設けることを努力義務に求めており、中でも条例は、業界団体に対応方針の「ひな形」を作ることを推奨している。
健康関連取引適正事業団は7月、顧問弁護士の監修を受けた「対策マニュアル」を加盟企業へ配布。加盟企業の間では以前から顧客による暴言等のカスハラが度々問題化。健取団が対応の仲介や法的アドバイスを行ってきたといい、このことも素早い動きに結び付いた。一方、日本訪問販売協会は「ひな形」の作成に消極的ではないものの、今のところ具体的な動きは見られない。 本紙アンケートでは、5割の企業がすでに方針を設けたか、設けることを検討している旨を回答したが、方針の必要性を感じながら「特に設けていない」とした回答も4割を占めた。対応が遅れている企業は急ぐ必要があるとともに、業界団体が支援の体制を整えることの重要性も増している。