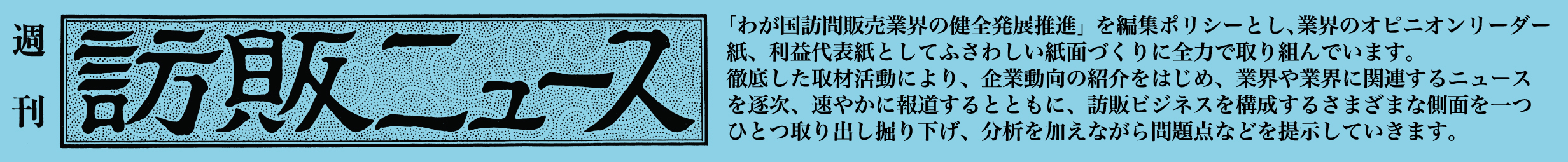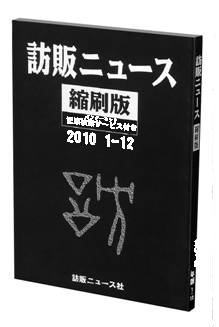都道府県の特定商取引法執行 埋められるか? 処分数ギャップ
表は1997年度から2018年度までの特商法処分件数を都道府県毎に並べたものだ。
過去年間の累計数は、業界にもその名を知られる〝特別機動調査班〟をもつ東京都が、296件でダントツのトップ (業務停止命令、指示、業務禁止命令の延べ件数)。これに埼玉県の158件、静岡県の78件、北海道の57件、神奈川県 の50件が続き、トップ5を首都圏の3都県が占めた。静岡県、北海道も以前から処分に熱心な道県として知られる。
他方で表からは、処分数の少ない下位の府県とのギャップも歴然。ワーストは福井県、宮崎県、沖縄県の3県が各1件で 並び、20年間の累計処分件数が二ケタに満たない府県は実に県におよぶ。
また、ある程度の処分数をもつように見えても、近年は処分を行ったことがない府県が存在 (表中で★のついた府県)。累計処分数が二ケタのうち岐阜県(18件)、兵庫県(18件)、岩手県(13件)、京都府(11件)、 秋田県(10件)の5府県は、14~18年度における処分数がゼロとなっている。全体では16府県が該当。都道府県の3分の1 は直近5年間の処分実績をもたないことになる。 18年度の1年間に絞ると、処分を行ったのは19都道府県にとどまり、残 り6割は執行ゼロ。表のようなギャップを生む最大の理由は、特商法執行に割く予算と専従人員の規模にあるが、処分を重 ねることで蓄積される執行ノウハウの差も大きい。このため、執行に熱心な都道府県ほど処分数を増やし、消極的なほど 処分を行わないという格差を広げることになる。
消費者行政周辺では、この〝処分数ギャップ〟の解消を訴える声が以前から根強い。近隣の都道府県や経済産業省の地方 局が連携する〝同時処分〟は、処分実績に乏しい府県の力量を高める役目も果たしているが、さらに抜本的な対策、取り組み を求める意見が常に叫ばれてきた。
そのような意見が改めて意見書の形で出されたのが7月。提出者は日本弁護士連合会で、消費者大臣や消費者庁長官、都 道府県知事に宛てた「特定商取引法の執行力強化に関する意見書」で、主に組織・人員、財源などの強化を求めた。提出の タイミングは、国や都道府県が来年度予算案の作成にかかる時期に合わせたものだ。
ここで注目されたのが、特商法の執行を専門とする部署を各都道府県に設けるという提案。意見書では、都道府県への アンケート調査の結果、〝特別機動調査班〟のような執行専門部署をもつ都道府県は20自治体に過 ぎないと指摘。さらに、同部署の中で執行ノウハウを蓄積・継承していくため、人事異動があっても担当職員の半数を残 せるように常時複数名の配置が必要と求める。
意見書では法改正の必要性にも触れ、処分を検討していた事業者が違法業務を明確に中断した場合も処分が可能なことを 明文化すべきと指摘。アンケートによれば12の都道府県が、候補の事業者が廃業・移転等して処分できなくなったことがあ ると回答したという。
この夏は、〝処分数ギャップ〟の解消を数値目標化しようとする動きも浮上した。地方消費者行政を強化・推進するため、 来年度以降の新たな〝5カ年強化作戦〟の方向性を検討していた、消費者庁の「地方消費者行政強化作戦2020策定に関 する懇談会」での議論だ。
懇談会では、特商法をはじめとする消費者関連法の執行実績に欠ける府県が少なくない状況が問題視され、事務局が作成 した報告書の原案で法執行の数値目標が盛り込まれなかったことにも複数の委員が反発。「執行をやったことがないところ ほど最初のハードルが高い」「すべての都道府県が執行経験をもつことができるような支援を」などとして、全都道府県が 1件以上の執行を行うことを〝5カ年強化作戦〟の目標にしようとする機運が生じた。
最終的に別の委員らの反対もあって見送られたものの、これに代わる目標として9月の報告書は、地方の執行担当職員 が国等の法執行研修へ参加する率を高める案に言及。他の政策目標では地方職員の研修参加率を80 %以上に設定することを求めており、実際に〝5カ年強化作戦〟へ反映された場合、来年度以降の地方処分に変化をもたらす 可能性も考えられる。
一方、日弁連や懇談会のような要請は、以前より繰り返し行われてきたことでもある。
17年8月には、消費者委員会が「消費者行政における執行力の充実に関する提言~地方における特商法の執行力の充実に 向けて~」をまとめ、消費者庁に提出。都道府県の法執行担当職員へのアンケートとヒアリングで課題を洗い出し、同庁に よる執行ノウハウのマニュアル化、消セン相談段階における違法行為の聞き取り、銀行など取引先への報告徴収、都道府県 および経産省地方局が連携する「連絡会議」の開催数引き上げ、行政指導なしの直接処分等々、地方の処分の底上げにつながる数々の具体アイデ アをまとめていた。
が、消費者委員会事務局によれば、提出から2年を経過した現在、「(提言書の)成果として出せるものはない」。提言を受けた取り組みの 状況を同庁にヒアリングすることも「未定」とした。都道府県の特商法執行強化を支援する国の取り組みは今のところ鈍いようだ。