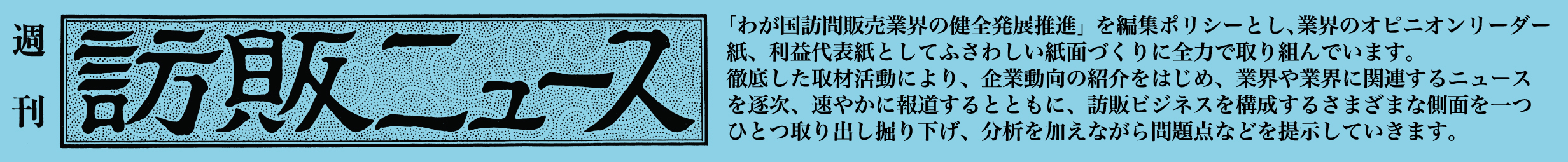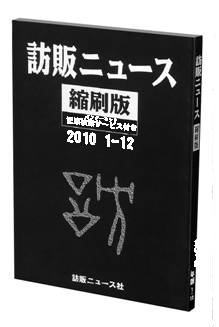書面電子化「施行後2年見直し」の行方 制度開始後の利用状況、取引対策課が「検討」着手
実態調査で提言
同意書面の電磁的提供、対象範囲拡大など
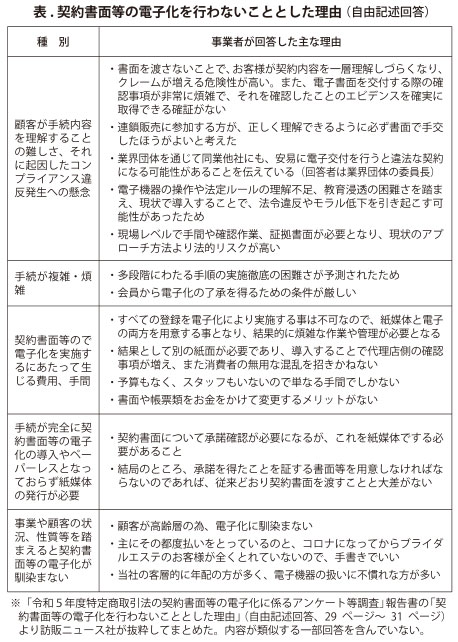
見直し規定、6月発動
「政府は、附則第一条第三号に掲げる規定の施行後二年を経過した場合において、同号イ及びロに掲げる改正規定による改正後の規定の施行の状況について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。」。
21年6月に成立・公布された改正特定商取引法および預託法において、附則の第6条に盛り込まれた規定だ。「附則第一条第三号」の「イ」「ロ」は、「イ」が特商法の書面電子化制度、「ロ」が預託法の同制度を指す。
書面電子化制度が施行されたのは23年6月。したがって、今年6月をもって施行から2年を経過した。附則第6条の「施行後2年見直し」規定が発動したこととなり、消費者庁は両法律の書面電子化制度の利用状況等について検討を行わなければならない。
改正法が施行されて一定の年数を経過した時点で、施行状況に検討を加えることを定めた附則は珍しくない。13年に施行された改正消費者安全法は、「施行後5年見直し」規定に基づく検討を18年に実施。翌年、施行状況が消費者庁から消費者委員会に報告された。
「5年見直し」で溝
この時、取引対策課は、同規定に基づく検討により、訪問販売への不招請勧誘規制導入が議論となる可能性を示唆。実際に、特商法の見直しを議論した15年の消費者委員会で、大きな論争に発展した。
一方、17年に施行された改正特商法の「施行後5年見直し」規定は、これに基づく検討が行われたかどうか見解が分かれている。
書面電子化制度は21年改正で導入され、23年にスタートした。改正は、17年の施行から4年後のため、5年規定をクリアしている。21年改正では、クーリング・オフの電子化と、業務禁止命令の効力を拡大する見直しも行われた。
しかし、「特商法の抜本的改正を求める全国連絡会」をはじめとする全国の消費者団体と弁護士会は、16年改正で見送られた訪問販売の不招請勧誘規制について検討が加えられていない旨を主張。
同規制を電話勧誘販売にも導入することや連鎖販売取引の開業規制、ネット通販の行政規制強化を議論することを求めている。同様の主張は、全国各地の地方議会117カ所(24年7月時点)が意見書として採択した。
消費者庁は、21年改正で「施行後5年見直し」の検討は行われたとの立場を取るため、大きな溝を生んでいる。
預託法でも利用皆無