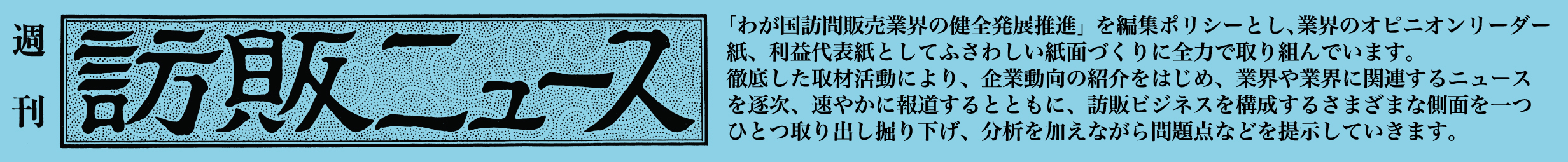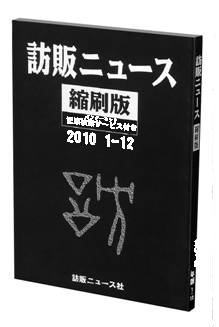シリーズ・特商法改正の行方 消費者庁 取引対策課「報告書」、異例の反発
日弁連「多くの疑問点」、新長官「真摯に受止め」
「脆弱性」の捉え方、消費者委答申と「齟齬」

▲取引対策課長の懇談会「デジタル社会における消費取引研究会」の報告内容に対して、日弁連は、消費者保護の観点から複数の問題点を指摘する意見書(=写真)を提出
課長の「懇談会」
「多くの疑問点がある」とされた報告書は、昨年6月、取引対策課の伊藤正雄課長(当時)が自身の「懇談会」として立ち上げた「デジタル社会における消費取引研究会」(研究会)の議論を整理したものとなる。「デジタル社会における消費取引についての対応のあり方に基軸を据えること」(報告書より)を目的に、計9回の会合がもたれ、今年6月に公表された。
発足の理由は、デジタル化の急速な進展にともなうEC取引の広がりと多種多様化に法規制が追い付いておらず、悪質事業者の取り締まりが困難になっているというもの。伊藤課長は初回会合で「デジタルは横串的で境界がない世界」「そこにラグが発生する。そこをどう埋めていくか」と述べ、デジタル社会における効果的対応策について議論を求めた。
経済に「過度に配慮」
報告書は、デジタル社会における消費者取引政策の「基軸」について、「自由主義国家における原則と例外措置に基づく考え方に立って、極力私人間の契約・取引に対して国家が干渉せず、個人の意思を尊重する原則の下での制度設計とすべき」と言及。また、「デジタル取引のリスクを過大に評価し、リアルでの取引以上にケアを強めると自主性や社会進展のための挑戦をより損なわせる側面がある」とした。
これに対して、日弁連の意見書は、デジタル社会の進展が消費者に様々な恩恵をもたらす面がある一方で、デジタル分野の消費者被害を放置すれば進展を逆に阻害しかねず、「消費者法制の更なる充実が強く求められている」「(報告書の)方向性に拘泥することなく、飽くまで消費者保護を基軸として行われるべき」と強調。
消費者保護と公正取引の確保には「一定程度普遍性のある規制を導入することが不可欠」「『消費経済市場への影響』に過度に配慮して消費者保護や市場の公正性を劣後させることには慎重であるべき」と求めた。
「肩書」除外、要求