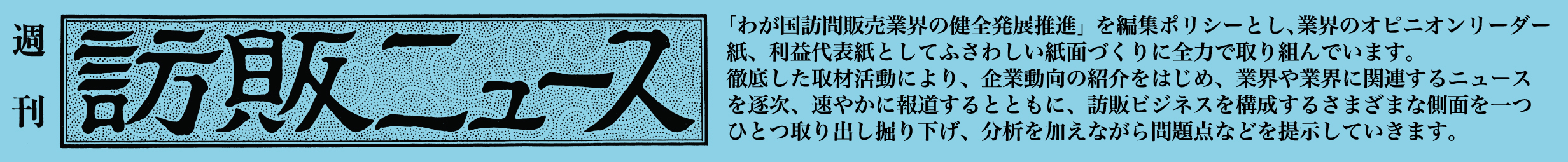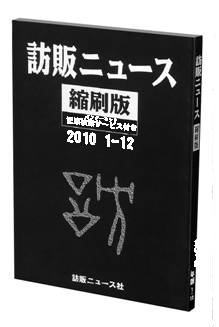消費者被害の拡大防止 消費者庁委託の「研究会」
裁判所の差止命令「従うこと期待できない」
注意喚起の効果、消費者安全法で「可能」
「ジャパンライフ」事件等に代表される深刻な消費者被害の拡大を早期に防ぐことを目的に、消費者法において、行政が裁判所に差止め命令を申し立てることができる制度のあり方などを議論していた消費者庁の有識者会議は、消費者安全法による勧告等の運用強化に取り組むことが重要とする報告書をまとめた。差止め命令制度は、悪質事業者に対する効果が期待しにくく、裁判所による迅速な違法性の判断が難しいと考えられることなどが指摘された。差止め命令による注意喚起の効果は、消費者安全法でも同様の効果を得ることが可能とされた。
2年前、自民が提言書
委員は、行政法や民法・刑法等に詳しい大学教授5人。7月~今年2月に計7回を開き、うち2回で弁護士ヒアリングを行った。 大規模な被害が拡大しているにもかかわらず、現行法で早期対応が難しい事例を念頭に、主に、消費者庁が裁判所に緊急差止め命令を申立てることができる制度について議論していた。消費者安全法の勧告制度等の運用についても議論した。
研究会に先立ち、23年12月、自民・消費者問題調査会が消費者庁長官に消費者法制度のパラダイムシフト推進等を求める提言書を提出。この中で、悪質・深刻な被害の急拡大に対応する方策の一つとして、「裁判所を介した手続の活用も含めた実効性の高い手段等が考えられる」と求められていた。
「まず行政が取組むべき」